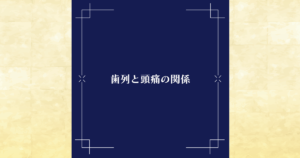
慢性的な頭痛に悩んでいるという人は多いのではないでしょうか。
その中には、なぜ頭痛が起こっているのか原因がはっきりしていないという人もいます。
実は、頭痛に歯列が関係していることもあることをご存じでしょうか。
頭痛と歯列が関係あるといわれても、ピンとこない人も多いでしょう。
歯列と頭痛にどのような関係があるのか解説します。
歯列は頭痛の原因になるのか
歯並びが正しい状態であれば頭痛の原因にはなりませんが、悪い場合にはその限りではありません。
なぜなら、歯並びが悪いと噛み合わせも悪くなってしまうからです。
噛み合わせが悪いと、咀嚼する際、顎にかかる負担が大きくなります。
顎にかかる負担が大きいと周囲の筋肉が緊張状態になるため、血流が妨げられて頭痛や肩こりの原因になってしまうのです。
また、噛むときに左右のどちらかに偏っている場合にも、頭痛の発生原因となることがあります。
頭痛の原因となる歯列
歯列が悪い状態を不正咬合といいますが、頭痛の原因となるのはどのようなものでしょうか?
まず挙げられるのは、下顎が上顎よりも前に出ている受け口です。
噛み合わせが逆になり、活舌が悪いケースも多いため、生活するうえで多くの支障が生じるでしょう。
また、歯並びがガタガタになっている叢生も頭痛の原因になりえます。
叢生は代表的な不正咬合で、八重歯もその一種です。
叢生は頭痛以外の問題を引き起こす可能性もあります。
なぜなら、歯並びが乱れているため、歯磨きをしても磨けない部分が出てしまうからです。
汚れが残り、虫歯や歯周病になりやすいのが特徴です。
さらに、歯の間の隙間が大きい空隙歯列も頭痛の原因になる恐れがあります。
すきっ歯とも呼ばれる空隙歯列は、口内を乾燥させるだけでなく、虫歯や奥歯を失う原因になることもあり、注意が必要です。
歯をしっかりと噛み合わせたときに前歯がかみ合わず、隙間ができる状態のことを開咬といい、前歯で噛み切ることができない状態です。
開咬も頭痛の原因になる可能性があります。
奥歯にかかる負担が大きいため、奥歯が虫歯になるリスクが高まります。
上の前歯が突出している出っ歯は、頭痛を引き起こすだけでなく、放置すると顔のゆがみの原因になることもあるでしょう。
まとめ
頭痛に悩む人は少なくありません。
何とかならないかと思っていても、原因を明らかにしないまま、鎮痛剤を服用してやり過ごすケースもよくあるでしょう。
頭痛にはさまざまな原因がありますが、歯並びの悪さもその一つです。
歯並びが悪い状態を不正咬合といい、特に受け口や叢生、出っ歯、すきっ歯、開咬などの不正咬合であれば、頭痛の原因となる可能性が高いでしょう。
頭痛に悩んでいる人は、歯並びが正しい状態かどうか調べることをおすすめします。
成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。
患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております。